三津浜歴史探訪 その9 「お茶屋井戸」
- Tatsuya Sugimoto
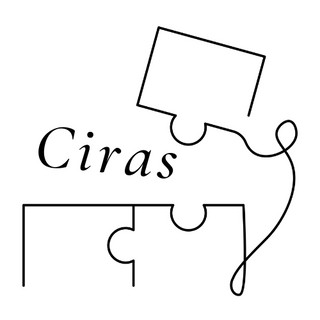
- 2012年7月3日
- 読了時間: 1分
更新日:2024年10月22日
松山市立三津浜小学校の校舎南側のグランドの脇に、藩政時代から「お茶屋井戸」と呼ばれている井戸があります。
江戸時代(1603~1867)、徳川幕府は全国の大名を治めるため参勤交代という制度を設けます。松山藩の大名は当然のことながら江戸へ行くのに船を利用しなければなりません。船着き場は三津の港でですから、以前(その5)ご説明した通り、帆船までの送り迎えを艀(はしけ)とう小舟でおこなっており、潮待ちや風待ちの休憩場所が必要でした。そこで、休憩地として適したところを模索します。
ところが、三津浜は海が近く真水の出る井戸がなかなか見つかりません。苦労の末、やっとこの場所を見つけ出し良質の真水が出たので井戸を掘り、ここに休息場所として「お茶屋」を建てたのです。
当時の建物は三階建ての立派なものだったと伝えられています。幕末に松山藩の学校である明教館(秋山兄弟、正岡子規、高浜虚子、河東碧梧桐などが通った学校)の分校となり、明治20年(1887年)三津浜尋常小学校になってから現在に至っています。




